「三菱 自動車 買っ て は いけない」と検索したあなたは、おそらく三菱自動車に対して何らかの不安や疑問を抱えているのではないでしょうか。「三菱自動車はあんまりよろしく無い事を聞きますが本当?」「三菱自動車買ってはいけませんか?」といった声がネット上には多く見られます。本記事では、そうした疑問に対し客観的な視点で情報を整理し、なぜそう言われるのかを明らかにしていきます。
かつて一世を風靡した三菱ですが、現在では「三菱 自動車 売れない理由」や「三菱自動車 恥ずかしい」といったキーワードで話題に上がることも少なくありません。特に「デリカミニ 買っては いけない」といった車種単位での評価や、「三菱の車乗ってるやつ」に対する世間の目も一部では厳しいようです。
また、「三菱 自動車 壊れやすい」といった品質面の不安、「三菱自動車 クズ」「三菱自動車 潰れろ」といった過激な意見が見られるのも事実です。それでもなお、「三菱自動車 なぜ潰れない」「三菱自動車 買う人いるの?」という声もあるように、支持層が存在するのもまた事実です。
この記事では、「三菱 自動車 やめとけ」といったネガティブな意見の背景にある根拠を一つ一つ整理し、どのような点に注意すべきかを丁寧に解説していきます。購入を検討している方も、すでに候補から外そうとしている方も、判断材料としてご活用ください。
-
三菱自動車の過去の不祥事や企業体質
-
現在の車種ごとの評判や品質傾向
-
購入後のトラブルや不満事例
-
三菱自動車が他メーカーと比較して劣る点
三菱自動車は買ってはいけない理由とは?

DALL·E 2025 03 30 14.57.46 A 16 9 image showing a person standing in front of a car dealership, looking thoughtfully at a Mitsubishi like car (generic design, no visible logos)
・三菱自動車買ってはいけませんか?
・三菱自動車が売れない理由を解説
・三菱自動車は恥ずかしいとされる背景
・デリカミニを買ってはいけない理由
三菱自動車はあんまりよろしく無い事を聞きますが本当?
はい、三菱自動車に関して「よろしくない」という評価が存在するのは事実です。ただし、その背景には過去の不祥事や企業体質、製品品質の課題など、複数の要因が絡んでいます。
まず過去のリコール隠し問題は、多くの人に強く印象づけられています。2000年から2004年にかけて発覚した一連のリコール隠し事件では、欠陥を報告せずにこっそりと「ヤミ改修」と呼ばれる非公式な修理対応を行っていました。これにより、事故が発生したケースもあり、消費者の安全意識を裏切る行為として社会的に大きな非難を浴びました。
また、2016年には燃費データの不正操作が発覚し、これも信頼性を大きく揺るがす出来事となりました。この不正は法令で定められた測定方法ではなく、社内で勝手に都合の良いデータを使用するというもの。結果として、燃費性能が実際よりも良く見えるよう偽装されていたのです。この一件により三菱は日産の傘下に入り、経営再建を図ることとなりました。
さらに、現在においても「企業文化が改善されていないのではないか」という疑念を持つ声があります。不祥事後の社内体制の変化や改革の進捗が見えにくいことが、未だ「よろしくない」と感じる理由の一つでしょう。
もちろん、すべての車種が問題を抱えているわけではなく、耐久性や性能面で一定の評価を受けているモデルも存在します。ですが、これまでの経緯から「三菱車を選ぶのは少し不安」という印象を持つ消費者が多いのも現実です。
三菱自動車買ってはいけませんか?
三菱自動車を買ってはいけないとまでは断言できませんが、購入に際しては注意が必要です。特に信頼性や品質に重きを置く方にとっては、慎重な判断が求められるメーカーの一つです。
三菱車に関する否定的な意見の多くは、企業としての信頼性に起因しています。過去に起きたリコール隠しや燃費データの改ざんといった問題は、単なる一時的なミスではなく、企業体質に関する深い課題を浮き彫りにしました。その後も「本当に体質が変わったのか」と疑問視する声は絶えません。
加えて、実際の所有者からも品質に関する不満が寄せられています。例としては、新車で納車された直後にドアに凹みがあったり、エアコンや電装系に不具合が発生したりするケースも報告されています。このようなトラブルは、日常的な利便性や安心感を損なう要因になります。
ただし、一方で肯定的な意見も存在します。たとえばアウトランダーPHEVは、電動SUVとして高い評価を受けています。また、価格設定が比較的抑えられていることから、コストパフォーマンス重視の方には選択肢の一つとなり得るでしょう。
このように考えると、「買ってはいけない」と決めつけるのではなく、モデルごとの性能や評判、使用環境との相性をきちんと確認することが大切です。過去の問題を知った上で、それでも納得できるポイントがあるのであれば、選択の幅として残すことも可能です。
三菱自動車が売れない理由を解説

DALL·E 2025 03 30 14.58.57 A 16 9 image designed like a YouTube thumbnail or blog banner. The background shows a modern car dealership with few customers, giving a subtle impres
三菱自動車が日本国内で苦戦している理由は、一つではなく複数の要因が重なっています。企業の信頼性、商品ラインアップの魅力、そして国内市場に対する姿勢など、様々な視点から検証する必要があります。
第一に挙げられるのは、過去の不祥事による信頼性の低下です。リコール隠しや燃費不正のような重大な問題は、企業イメージを大きく傷つけました。こうした不祥事の記憶は長く残るもので、現在でも「三菱は信用できない」という印象を持つ人は少なくありません。
次に、魅力的な車種が少ないことも影響しています。かつては「ランサーエボリューション」や「パジェロ」など、多くのファンを持つ車種が存在していました。しかし近年はそのような象徴的なモデルが廃止され、SUVや軽自動車に特化した構成になっています。その結果、他社のラインアップと比べて選択肢が狭く、商品力が不足していると見なされています。
さらに、日本市場を重視していない姿勢も販売不振の一因です。三菱はアセアン地域での成長に力を入れており、その影響で国内市場では新型車の投入が遅れたり、マーケティング戦略が後手に回ったりすることがあります。2016年から約4年間、新型車を国内に投入しなかったという事実も、国内ユーザーの心を離れさせる一因となりました。
このように、売れない理由は単なる製品の問題ではなく、企業の戦略や過去の信用問題、そして市場との向き合い方に根本的な課題があると言えます。信頼の再構築と商品企画の見直しがなされない限り、日本国内での売上回復は難しいでしょう。
三菱自動車は恥ずかしいとされる背景
三菱自動車が「恥ずかしい」と言われてしまう背景には、過去の不祥事のインパクトと、その後のブランド回復が不十分であるという印象が関係しています。自動車という商品は、単なる移動手段であるだけでなく、その所有者の価値観や生活スタイルを映す存在でもあります。そのため、選ぶ車のブランドが世間的に悪いイメージを持たれていると、オーナー自身にも影響を及ぼしてしまうのです。
まず、三菱自動車に対する社会的なイメージを大きく損ねたのが、2000年代初頭のリコール隠し事件です。この時、重大な欠陥を運輸省に報告せず、ひそかに修理する「ヤミ改修」が行われていたことが発覚しました。中には命に関わる事故にもつながる事例が含まれており、企業としての倫理観が問われる大問題に発展しました。
さらに、2016年には燃費データの改ざんが明らかになり、「またか」という世間の反応を招いてしまいました。この出来事によって、再び信頼を大きく失い、日産の傘下に入ることとなりました。こうした経緯があるため、三菱の車に乗っていることが「まだあのメーカーを選ぶの?」といった目で見られてしまう原因となっています。
また、現在でも国内での存在感が薄くなっており、「売れていないメーカーの車」というイメージも先入観を助長しています。特にパジェロやランサーエボリューションといった名車の時代を知っている人にとっては、今のラインナップに魅力を感じにくいという声も少なくありません。
このように、過去の不祥事の記憶と現在のブランド力の低下が合わさることで、三菱車を選ぶことが「恥ずかしい」と揶揄される背景を形成しているのです。
デリカミニを買ってはいけない理由
デリカミニはユニークな見た目やアウトドア向けの設計で注目を集めていますが、すべてのユーザーにおすすめできる車とは限りません。用途や利用環境によっては、購入後に後悔する可能性もあるため、注意が必要です。
まず最も指摘されているのが、マイルドハイブリッドシステムの性能に関する問題です。このシステムは短距離の繰り返し走行など、特定の条件下では十分に機能しない場合があります。実際、バッテリーが頻繁に充電されない環境ではハイブリッド機能が停止し、結果として燃費が悪化する事例が報告されています。カタログ値と実燃費に差があるという声もあり、燃費性能を期待して購入した方にとっては大きなギャップとなるでしょう。
さらに、初速の加速性能にも不満の声が上がっています。車両重量がやや重めであることから、出だしがもたつくという印象を受ける方が多く、都市部の信号スタートや高速道路での合流時にストレスを感じる場面もあるようです。
加えて、価格設定にも疑問が残ります。軽自動車というカテゴリの中では比較的高額で、最上位グレードともなるとコンパクトカーと同等の価格帯になります。多機能であることが裏目に出て「こんなに装備いらなかった」と感じる方も一定数存在しています。
また、初期トラブルの報告も見逃せません。LEDウインカーの不具合や、電装系統のエラーなど、細かい部分での品質にバラつきがあるようです。新型車特有の問題ではあるものの、こうした不具合が続くと修理や対応に時間とコストがかかり、手間が増えてしまいます。
最後に、デリカミニのコンセプトが「アウトドア向け」である点も考慮が必要です。悪路走破性やルーフレールなど、都市部の日常利用では活かしきれない機能が搭載されているため、使い方によってはオーバースペックになってしまう可能性もあります。
このように、デリカミニは見た目や機能性に魅力を感じる人も多い一方で、運転環境や目的を誤るとデメリットが際立つモデルでもあります。購入前には、自身のライフスタイルに合った車かどうかを慎重に見極めることが重要です。
なぜ三菱自動車買ってはいけないのか?

DALL·E 2025 03 30 14.59.40 A 16 9 YouTube style thumbnail image with a dramatic and curious tone. In the background, there’s a generic, Mitsubishi like car (no logo) under a clo
・三菱自動車は壊れやすいと感じる原因
・三菱自動車クズと呼ばれるワケ
・三菱自動車潰れろとまで言われる理由
・三菱自動車はなぜ潰れないのか?
・三菱自動車を買う人いるのはなぜ?
・三菱自動車やめとけという声の根拠
・総括:三菱自動車は買ってはいけない?
三菱の車乗ってるやつの傾向
三菱の車に乗っている人たちには、ある程度共通する特徴や傾向が見られます。特に、一般的な評価やブランドイメージに左右されにくい独自の価値観を持っている方が多いのが印象的です。
まず、アウトドア志向のユーザーに支持されている傾向があります。これは、三菱自動車が長年にわたり四輪駆動(4WD)技術に力を入れてきた背景が関係しています。パジェロやデリカなどは、悪路走破性に優れた設計がされており、キャンプや登山など自然と関わる趣味を持つ方から特に支持されています。舗装路以外の道を走る機会が多い人にとって、三菱車は頼りになる存在です。
また、他人と被りたくないという思いから三菱車を選ぶ人も少なくありません。現在の日本国内ではトヨタやホンダ、スズキといったブランドが主流を占めていますが、あえてその流れから外れ、個性を重視するスタイルを好む人が三菱を選ぶケースがあります。ブランドとしての人気度よりも、自分に合った機能やデザインを優先するという価値観が背景にあるのです。
そして、価格の安さや値引きのしやすさに魅力を感じて購入する人も一定数います。他メーカーよりもディスカウントの幅が大きく、総額を抑えて新車を購入できる点は、家計を重視する層にとって魅力的です。このような実用性を重視する層も、三菱車のオーナーとして多く見られます。
つまり、三菱の車に乗っている人は「機能性重視」「アウトドア志向」「他人と違う車を持ちたい」「コストパフォーマンス重視」といった価値観を持っていることが多いと言えるでしょう。他人の評価よりも、自分にとっての使いやすさや好みに基づいた選択をしている点が共通しています。
三菱自動車は壊れやすいと感じる原因
三菱自動車が「壊れやすい」と感じられる背景には、いくつかの具体的な要因があります。これは単なる印象だけでなく、実際のユーザーの声や過去の不具合報告にも基づいています。
まず、過去に起きた品質に関する不具合が記憶に残っている人は少なくありません。例えば、エアコンや電装系統の不具合、パワーウィンドウの動作不良といった細かなトラブルが多く報告されていました。こうした部品のトラブルは走行には直接関係しないとはいえ、日常の使い勝手に大きな影響を及ぼします。「細かい部分がすぐ壊れる」という印象が定着する一因となっています。
また、設計や生産体制の面でも、他社に比べてコスト削減の影響を受けやすかったと言われています。開発費や試験工程を縮小した結果、製品の完成度が不十分なまま市場に出てしまったケースがあるという指摘もあります。たとえば、アウトランダーPHEVにおいてはセンサーの設計ミスによる大規模なリコールが発生しており、こうした事例が「壊れやすい」という印象を強めています。
さらに、初期不良の報告数が多いことも要因の一つです。納車後すぐに部品交換が必要になったり、サービスセンターに通う回数が多くなることがあると、どうしても信頼感は薄れてしまいます。車の購入は高額な買い物ですから、「しっかり作られていないのでは?」という疑念が芽生えるのも当然でしょう。
一方で、すべての車種が壊れやすいわけではなく、パジェロやランサーなど一部のモデルでは高い耐久性を評価する声もあります。そのため、「壊れやすい」と言われる原因は、モデルの違いや生産時期の影響も含まれていると考えるのが妥当です。
三菱自動車クズと呼ばれるワケ
三菱自動車が「クズ」とまで言われてしまうことがあるのは、過去の不祥事によって企業イメージが著しく損なわれたためです。このような強い言葉が使われる背景には、単なる製品の問題だけでなく、企業体質や社会的責任のあり方に対する強い批判が含まれています。
もっとも大きな要因は、2000年代初頭に発覚したリコール隠し事件です。これは単なる不備の隠蔽ではなく、命に関わる重大な欠陥を国に報告せずに内密に修理対応を行っていたという事案であり、当時の社会に大きな衝撃を与えました。実際に事故や死傷者が出たこともあり、企業としてのモラルが問われる問題となりました。
加えて、2016年には燃費データの改ざんという新たな不正も明らかになりました。これは法令違反だけでなく、消費者を意図的に欺いた行為として、再び強い非難を浴びることになります。「もう信じられない」と感じたユーザーや業界関係者の中には、感情的な表現として「クズ」という言葉を使った人も少なくなかったでしょう。
また、これらの問題に対する企業の対応も不十分と見なされたことが、批判に拍車をかけました。謝罪や再発防止の姿勢が形式的に見えてしまったり、経営陣の刷新が遅れたりといったことから、「体質が変わっていない」という不信感が根強く残ることになります。
ただし、こうした評価は過去のイメージに基づくものであり、現在では体質改善や技術開発への投資も進められています。それでも、「一度失った信頼を取り戻すのは容易ではない」という事実が、現在も三菱に厳しい目が向けられている理由の一つです。購入を検討する際は、感情的な評価だけでなく、最新の製品性能や企業の取り組みについても冷静に見極めることが重要です。
三菱自動車潰れろとまで言われる理由
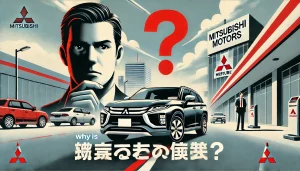
DALL·E 2025 03 30 15.00.49 A 16 9 YouTube style thumbnail image with a dramatic and investigative tone. In the background, a generic, Mitsubishi like car (no logos) is parked ne
「潰れろ」とまで強い言葉で非難される自動車メーカーは多くありませんが、三菱自動車がその対象になってしまうのは、過去の重大な不祥事と、それに対する消費者の深い失望感が根本にあります。単なる製品の不具合ではなく、企業の体質や倫理観に対する怒りが「潰れてしまえ」という感情的な言葉に表れているのです。
特に印象が強いのは、2000年代初頭に発覚したリコール隠し事件です。これは通常の不具合報告を怠るだけでなく、危険な欠陥を知りながらも国に届け出ず、内密に修理を行っていたという行為です。実際に死亡事故が発生しており、企業としての責任感が問われました。このような背景があるため、「安全より利益を優先した企業」というレッテルが貼られたままになっています。
加えて、2016年の燃費データ改ざん問題も追い打ちをかけました。軽自動車の性能を偽装して販売していたことが明らかになり、「またか」「反省していない」と感じた消費者の間で批判が再燃しました。こうした連続する不正により、信頼回復の機会すら奪われる形になってしまったのです。
さらに、これらの問題に対して「十分な説明責任が果たされていない」「経営陣の入れ替えが不十分」といった声も根強く、企業改革が見えにくいことも不信感の原因となっています。消費者としては「また同じことを繰り返すのでは」と不安を感じざるを得ず、それが「潰れてしまえ」といった極端な意見に繋がっているのでしょう。
このように、三菱自動車に対する強い反発は、単なる車両の評価を超えて、企業としての姿勢や信頼性の問題に起因しています。感情的な表現ではありますが、その背景には長年積み重なった失望と不満があるのです。
三菱自動車はなぜ潰れないのか?
これまで何度も経営危機に直面しながらも、三菱自動車は現在も存続し続けています。その理由は、単に資金繰りが上手くいっているからではなく、複数の経営戦略と外部支援が複雑に絡み合っている結果です。
まず大きいのが、アライアンスによる支援体制の存在です。2016年の燃費不正問題の後、三菱自動車は日産自動車の傘下に入りました。これにより、技術や生産体制の共有が進み、単独では難しかった規模の投資や開発が可能になっています。特にPHEV技術やプラットフォーム開発においては、他社との連携が大きな武器となっています。
次に、海外市場での販売好調も経営を支える柱です。日本国内では苦戦しているものの、タイやインドネシアなどのASEAN地域では、ブランド力が依然として強く、堅実な売上を維持しています。ピックアップトラックやSUVといったラインアップが現地ニーズにマッチしており、収益の大部分をこうした地域で確保している状況です。
また、直近の中期経営計画「Challenge 2025」では、固定費の削減と新技術への集中投資を掲げています。これにより、過去のような無理な拡大路線を改め、利益を重視した堅実経営への転換が図られています。こうした改革の成果として、赤字脱却や営業利益の黒字化を達成するなど、数値上の回復も見られています。
つまり、三菱自動車が潰れずにいるのは、経営の見直しとアライアンスの支援、そして海外市場での安定した収益構造があるからです。国内の評価が低くても、全体としては持ちこたえる力を持っている企業であることが分かります。
三菱自動車を買う人いるのはなぜ?
三菱自動車に対して否定的な声がある一方で、実際には今も多くの人が三菱車を購入しています。これには明確な理由があり、車を選ぶ基準やライフスタイルによっては、三菱車が非常に魅力的に映ることもあります。
まず注目されているのが、アウトランダーPHEVのような電動車における技術力です。三菱は世界初のプラグインハイブリッドSUVを商用化したメーカーであり、その技術力は国内外で高く評価されています。アウトドア志向のユーザーや、充電設備が整っている家庭環境では、走行性能と環境性能のバランスが取れたこのモデルは非常に重宝されています。
さらに、軽自動車部門においても一定の人気を保っています。例えば「デリカミニ」や「eKシリーズ」などは、独自のデザインや機能性で注目を集めており、特にファミリー層や地方在住者から支持を得ています。価格面でも競合他社と比べて手頃である点が、購入の後押しになっています。
また、三菱の4WD技術は非常に信頼性が高く、雪国や山間部などの過酷な環境に住む人々からは重宝されています。パジェロやデリカD:5といった車種は、悪路でも安定した走行ができる点で評価されており、そうした特定ニーズに強く応えるモデルが存在しているのです。
加えて、ディーラーでの大幅な値引きやキャンペーンなど、販売面での優遇も魅力の一つです。他社に比べて購入時のコストを抑えやすいため、「とにかく新車を安く手に入れたい」というニーズに応えることができます。
つまり、三菱自動車を買う人がいるのは、「技術」「価格」「用途」の面で他メーカーにはない強みがあるからです。ネガティブなイメージだけでは測れない実用的な価値が、今も一定の購入層を惹きつけているのです。
三菱自動車やめとけという声の根拠
「三菱自動車はやめとけ」といった意見が見られる背景には、過去の不祥事だけでなく、現在もなお残る企業体質への不信、そして製品に対する不安など、いくつかの明確な根拠が存在します。これらは感情的な批判というより、事実に基づいた意見であることが多く、購入を検討している人にとっては無視できない情報です。
まず第一に、三菱自動車は過去に重大な不祥事を何度も起こしており、それが長期的にブランドイメージに悪影響を与えています。2000年代に発覚したリコール隠しでは、欠陥を公表せずに内密で修理するという対応を長年行っていました。安全性に関わる問題が放置された結果、重大な事故も発生しており、企業倫理を疑問視する声が一気に高まりました。
さらに、2016年には燃費データの改ざん問題も明るみに出ました。法令に定められた測定方法を守らず、実際より良い数値を見せかけることで消費者を欺いたことになります。この不正行為により、三菱は日産の資本傘下に入り経営再建を余儀なくされましたが、「根本的な企業体質は変わっていないのでは」と疑う声はいまだ根強く残っています。
製品の面でも、不安材料は存在します。一部モデルでは初期不良や細かい不具合の報告が多く、品質管理の甘さを指摘する声が後を絶ちません。例えば、電装系のトラブルや内装部品の不具合など、日常的な使い勝手に関わる部分での信頼性が十分とは言えないケースがあります。こうした状況は、ユーザーに「また何か起きるのでは」という不安を与えてしまいます。
さらに、ディーラー対応についての評判も地域によって差があり、販売店によってはサービスに満足できなかったという声も見受けられます。これはブランド全体の信頼度を下げる要因にもなりかねません。
このように、「やめとけ」と言われるのは、企業の過去の行動や現在の信頼性に対する疑念、さらには製品の品質やアフターサポートに関する懸念が複合的に関係しています。購入前には最新の情報を確認し、特に評判の良くないモデルや販売店には注意を払うことが大切です。選択肢として三菱を検討する場合でも、慎重な判断が求められます。
総括:三菱自動車は買ってはいけない?
-
過去に複数のリコール隠し事件を起こしている
-
燃費データ改ざんの不正が発覚している
-
信頼回復への取り組みが不十分とされる
-
品質面での初期不良が繰り返し報告されている
-
電装系や内装部品の不具合が多い
-
ディーラー対応に地域差があり信頼性に不安がある
-
売れていないため所有が恥ずかしいと感じる声もある
-
モデルの魅力が乏しく選択肢が限られている
-
国内市場よりも海外重視の経営姿勢が見られる
-
企業体質の改善が進んでいないと指摘されている
-
値引きの幅が大きく、信頼より価格重視の印象がある
-
過去の不正によりブランドイメージが定着している
-
運転性能や使い勝手にバラつきがあるモデルも存在
-
一部の軽やPHEVは高評価だが全体の信頼には繋がっていない
-
消費者の間で「また何かあるのでは」という警戒心が強い
日産アリアが売れない原因を探る!購入前に知るべきポイント


