マイナンバーカードと運転免許証が一体化された「マイナ免許」とは何か、そしてその中でも特に関心の高い「マイナ 免許 証 ゴールド 見分け 方」について詳しく知りたいという方は少なくありません。この記事では、「マイナンバー免許証のゴールドとは?」という基本から、「マイナンバー免許証 ゴールドとブルーの見分け方ってマイナンバーカードになるとどう見る」のかという実際の確認方法まで、わかりやすく解説していきます。
2025年から導入されたこの新制度では、従来のように免許証の帯の色でゴールドやブルーを見分けることができなくなりました。そのため、マイナ免許証の見た目では区別がつかず、専用の読み取り機器やマイナ免許証読み取りアプリ、マイナ免許証 iPhoneでの操作が必要になります。
さらに、マイナ免許証のメリットとデメリットを比較しながら、「運転免許証のゴールドは何年でもらえる?」という疑問や、「ゴールド免許証を取得するとどんな優遇がありますか?」といった特典にも触れます。また、マイナ免許証を利用するために必要な準備や「マイナ免許証 切り替え 方法」、手続きができる「マイナ免許証 どこで」の情報も掲載。
一方、「マイナ免許証2枚持ち」といった柔軟な運用方法にも注目し、自分のライフスタイルに合った選択肢を考えるヒントもご紹介します。「マイナ免許証 いつから」の導入タイミングや、最新の運用状況も踏まえて、今後の手続きに備えましょう。
本記事では、マイナ免許証に関する最新情報をまとめ、初めての方でもスムーズに理解できるよう構成しています。今後の運転生活に役立つ知識として、ぜひご活用ください。
-
ゴールドとブルーの違いと確認方法
-
マイナ免許証の読み取り手段
-
ICチップ内の情報の見方
-
ゴールド免許の条件とメリット
・警察庁 マイナンバーカードと運転免許証の一体化に関する法改正
マイナ免許証ゴールド見分け方の基本知識
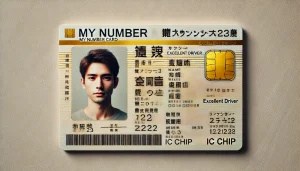
DALL·E 2025 03 29 08.59.09 A horizontal image (16 9 aspect ratio) showing a sample of a combined Japanese My Number Card and Driver’s License (マイナンバーカードと運転免許証の一体型カード). The card
・マイナンバー免許証のゴールドとは?
・マイナンバー免許証 ゴールドとブルーの見分け方ってマイナンバーカードになるとどう見る
・マイナ免許証のメリットとデメリット
・マイナ免許証 見た目
・マイナ免許証 iPhone
マイナ免許証とは
マイナ免許証とは、運転免許証の情報をマイナンバーカードのICチップに統合し、1枚のカードで本人確認と運転資格の両方を担う新しい形式の身分証です。2025年3月24日から希望者を対象に運用が始まりました。
これまでの運転免許証では、カード表面に免許の有効期限や帯の色(ゴールド・ブルー・グリーン)などの情報が視覚的に表示されていましたが、マイナ免許証ではそれらの情報はカードのICチップ内に格納される仕組みです。見た目は通常のマイナンバーカードと変わらず、運転免許として利用する際はICチップの読み取りが必要になります。
このような仕組みにより、利便性は大きく向上しています。例えば、引っ越しに伴う住所変更が市区町村の窓口だけで完了し、警察署に出向く必要がなくなります。また、優良運転者や一般運転者であれば、更新時の講習をオンラインで受講できるため、忙しい人にとっても手間が軽減されます。さらに、全国どこの都道府県でも免許更新が可能になった点も注目されています。
ただし、注意点もあります。マイナ免許証のICチップに記録されている情報は、専用アプリや読み取り機器を使わないと確認できません。そのため、紙の免許証に慣れていた人には不便に感じる場面もあるでしょう。加えて、紛失した場合の再発行には通常1ヶ月以上かかるため、急ぎで必要なときには困る可能性もあります。
このように、マイナ免許証は行政手続きの効率化や利便性向上を目的に設計された新しい制度ですが、デジタル管理への対応が求められるという面も併せ持っています。自分の生活スタイルに合っているかを考慮したうえで導入を検討することが大切です。
マイナンバー免許証のゴールドとは?
マイナンバー免許証のゴールドとは、従来の運転免許証と同じく「優良運転者」に交付される免許区分を意味します。カードの見た目には色が表示されなくなりましたが、ICチップ内にはしっかりとゴールド区分の情報が記録されています。
優良運転者とは、過去5年間にわたって無事故・無違反である人を指し、かつ免許を継続して5年以上保有していることが条件となります。この条件を満たすと、更新時にゴールド免許が交付され、有効期間は5年(70歳以上は短縮される場合あり)となります。
このゴールド免許には複数のメリットがあります。まず、更新手続きが簡単になり、講習時間は30分と短時間で済みます。さらに、手数料も他の区分より安く設定されています。自動車保険の「ゴールド免許割引」が適用されることもあり、年間の保険料が数千円から1万円程度安くなるケースも少なくありません。
一方で、ゴールド区分であることがカード表面で視認できないため、ICチップの情報を読み取れる環境がなければ第三者が判断するのは難しくなりました。レンタカーの利用時や各種手続きでゴールド免許であることを証明する際には、スマホアプリなどの補助ツールが必要になる場面もあるでしょう。
このように、マイナンバー免許証でもゴールド免許の制度は継続されていますが、確認方法が視覚から電子的な手段へと変わっている点には注意が必要です。
マイナンバー免許証 ゴールドとブルーの見分け方ってマイナンバーカードになるとどう見る
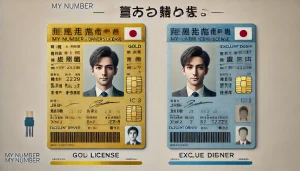
DALL·E 2025 03 29 09.00.14 A horizontal (16 9 aspect ratio) comparison image showing two combined Japanese My Number and Driver’s License cards side by side. One card represents
マイナンバー免許証になると、ゴールドとブルーの区分はカード表面から直接見分けることができなくなります。従来の運転免許証であれば、帯の色で一目瞭然でしたが、マイナ免許証ではICチップに情報が保存されているため、専用の方法で確認する必要があります。
その確認方法は主に3つあります。まず1つ目は「専用の読み取り端末」を使う方法です。警察署や運転免許センターなどに設置された機器にマイナ免許証をかざし、暗証番号を入力することで免許情報が表示されます。ここで、ゴールドやブルーなどの区分が確認できます。
2つ目は「マイナポータル」との連携です。スマートフォンやPCからマイナポータルにログインし、電子証明書を使って免許情報を表示させることで、自分の免許区分を確認することができます。ただし、事前に署名用電子証明書の設定がされていなければ閲覧できません。
3つ目は、スマートフォン向けの「マイナ免許証読み取りアプリ」の活用です。このアプリを使えば、NFC機能搭載のスマートフォンでICチップの情報を読み取り、自分の免許種別や有効期限などを確認できます。特にiPhoneユーザーであれば、アプリを使っていつでも手元で確認できる点が便利です。
ただし、これらの方法はいずれも「読み取り環境」が必要です。そのため、現時点ではすべての民間施設が対応しているわけではなく、場合によっては従来の運転免許証の提示を求められることもあります。
このように、マイナ免許証におけるゴールドとブルーの見分け方は、以前と比べて視覚的な判断ができなくなった分、デジタル機器の利用が前提となっています。利用時の環境や目的に応じた使い方を意識することが大切です。
マイナ免許証のメリットとデメリット
マイナ免許証には、利便性の向上や手続きの簡略化といった多くのメリットがある一方で、デジタル化特有の不安点や制約も存在します。ここでは、それぞれの側面を具体的に解説します。
まず、主なメリットとして挙げられるのは、行政手続きの一元化です。従来、住所や氏名の変更には、警察署や運転免許センターへの届け出が必要でした。しかし、マイナ免許証では、マイナンバーカードと情報が連携されているため、市区町村の窓口だけで変更手続きが完了します。この「ワンストップ化」は、特に引っ越しが多い人にとって大きな時短効果があります。
次に、講習や更新の利便性も向上しました。優良運転者や一般運転者であれば、更新時の講習をオンラインで受講することが可能になりました。これにより、平日の日中に免許センターへ出向く必要がなくなり、スケジュールの柔軟性が大幅にアップします。また、手数料も従来に比べて低く設定されており、経済的な負担も軽減される点も見逃せません。
さらに、全国どこでも更新できるという点もメリットです。従来の免許証では、基本的に居住地の管轄でしか更新ができませんでしたが、マイナ免許証では都道府県に関係なく手続きが可能になりました。単身赴任や学生など、居住地が変わる人にとっては特に便利です。
一方、デメリットもあります。最も大きな懸念点は「再発行の遅さ」です。マイナンバーカードを紛失した場合、再発行には最大で1ヶ月半かかることもあり、その間運転ができないリスクが生じます。また、カードに記載されている情報が限られているため、有効期限や免許区分などがすぐに確認できず、専用アプリや端末が必要になります。
もう一つの懸念は、個人情報の集中管理によるリスクです。運転免許情報だけでなく、氏名や住所、マイナンバーなど多くの情報が1枚のカードに記録されているため、万が一カードが盗難・紛失した場合の被害は大きくなります。情報漏えいに対する不安が完全に拭えない点は否めません。
このように、マイナ免許証は利便性を高める一方で、情報管理や紛失時の対応などに注意が必要です。導入を検討する際は、自身の生活スタイルやリスク許容度を踏まえて判断することが求められます。
マイナ免許証 見た目
マイナ免許証の見た目は、従来の運転免許証とは大きく異なります。一言で言えば、「マイナンバーカードそのもの」です。運転免許としての情報はすべてICチップ内に記録されており、カード表面には運転資格に関する表示は一切ありません。
従来の免許証には、名前、住所、顔写真、有効期限、免許の種類、帯の色など、視覚的に確認できる情報が多数印字されていました。しかし、マイナ免許証はそうした情報を省略し、代わりにICチップへ記録するという設計になっています。そのため、見た目だけでは一般のマイナンバーカードと区別がつきません。
提示する際にも注意が必要です。例えば、身分証明書として提出する場合、見た目では運転免許機能が含まれているかどうかが判断できないため、専用のリーダーやアプリによってICチップの中身を確認してもらう必要があります。これは、レンタカーの貸出や公的機関での手続きなど、運転資格を証明する場面では特に重要です。
このように、マイナ免許証の外観はシンプルで一見便利そうに見える反面、相手側の読み取り環境に依存するという点が課題になります。誰が見てもすぐに免許証だと分かる従来型とは異なり、デジタル機器による読み取りが前提になるため、社会全体がそれに対応しているかどうかも鍵となります。
見た目が変わることで生じるメリットとしては、カードの枚数が減ることが挙げられます。財布に入れるカードが1枚減るだけでも日常のストレスが軽くなると感じる人もいるでしょう。しかし一方で、見た目に何も表示がないことで起きる確認の手間も無視できません。
見た目がすっきりする代わりに、使い方や読み取りの仕組みに慣れる必要があるという点を理解しておくことが大切です。
マイナ免許証 iPhone
iPhoneを使えば、マイナ免許証の情報を手軽に確認することができます。専用アプリを利用することで、ICチップに記録された運転免許情報を読み取ることが可能となり、日常生活の中でも安心して活用できます。
具体的には、「マイナ免許証読み取りアプリ」をApp Storeからインストールし、iPhoneのNFC(近距離無線通信)機能を活用してマイナンバーカードを読み取ります。このとき、あらかじめ設定している4桁の暗証番号を入力することで、ICチップに記録された免許情報(免許の種類、有効期限、ゴールドかブルーかの区分など)を表示できます。
この方法は、免許証を持ち歩かずにスマートフォンで確認できる点が大きな利点です。特に有効期限を忘れがちな人にとっては、アプリで手軽にチェックできることが安心につながります。通知機能をオンにしておけば、更新期限が近づいた際にリマインドしてくれる仕組みもあります。
ただし、注意点もあります。まず、対応するiPhoneのバージョンはiOS 15以降に限られており、古い端末では利用できません。また、NFCの読み取り精度は機種や操作方法によって差があるため、最初はコツが必要です。カードを平らな場所に置き、iPhoneの背面をしっかり密着させることで読み取りやすくなります。
また、アプリで読み取った情報は、あくまで個人の確認用であり、運転資格の正式な提示にはなりません。公的な場で免許の提示を求められた際は、物理的なマイナンバーカード(マイナ免許証)そのものが必要です。
このように、iPhoneでの確認は非常に便利ではあるものの、すべての用途を代替できるわけではないという点には留意する必要があります。使い方を正しく理解して、日常の管理や確認に役立てることが重要です。
マイナ免許証ゴールド見分け方と関連情報

DALL·E 2025 03 29 09.00.16 A horizontal (16 9 aspect ratio) comparison image showing two combined Japanese My Number and Driver’s License cards side by side. One card represents
・ゴールド免許証を取得するとどんな優遇がありますか?
・マイナ免許証2枚持ち
・マイナ免許証 いつから
・マイナ免許証 切り替え 方法
・マイナ免許証読み取りアプリ
・マイナ免許証 どこで
・総括:マイナ免許証のゴールド見分け方
運転免許証のゴールドは何年でもらえる?
運転免許証のゴールドは、一定の条件を満たすことで初めて取得できます。単に長く運転しているだけでは自動的にゴールド免許になるわけではないため、取得のタイミングと条件を正確に理解しておくことが重要です。
まず、ゴールド免許を取得するためには、「免許を継続して5年以上保持していること」と「過去5年間に無事故・無違反であること」が必要です。ここで言う「無事故・無違反」とは、交通違反による行政処分が一切ない状態を指します。違反点数が1点でも加算されていれば、その時点でゴールド免許の対象外となります。
さらに、「過去5年間」というカウントの起点も少し注意が必要です。これは、次回免許証の更新日からさかのぼって5年間を指しており、免許更新の40日前(いわゆる基準日)までに違反があるかどうかで判断されます。たとえ5年近く違反がなかったとしても、その直前に軽微な違反をしてしまった場合は対象外となるため、油断はできません。
例えば、初めて運転免許を取得してから5年以上経過していても、その間に1度でもスピード違反や信号無視などがあった場合は、ゴールドではなくブルー免許が交付されます。無事故・無違反の状態を継続して保ち続けることがゴールド免許取得への近道です。
このように、ゴールド免許を取得できるかどうかは、日々の運転態度が大きく影響します。運転歴の長さよりも、「安全運転を継続していること」が何よりも評価されるという点を覚えておくとよいでしょう。
ゴールド免許証を取得するとどんな優遇がありますか?
ゴールド免許証を取得すると、手続きや費用の面でさまざまな優遇を受けることができます。これは優良運転者としての証でもあり、日々の安全運転が報われる仕組みと言えるでしょう。
まず大きなメリットとして挙げられるのが、免許更新の手間が大幅に軽減されることです。ゴールド免許の更新講習はわずか30分で済み、他の区分と比べて非常に短時間です。また、更新手数料も比較的安く、講習費用込みでも負担が少なくて済みます。忙しい社会人や高齢者にとって、これは非常にありがたい制度です。
また、ゴールド免許を持っていることで自動車保険の割引が受けられることも多くあります。保険会社によって割引率は異なりますが、一般的には5〜20%程度の割引が適用されることがあります。年単位で見ると数千円から1万円以上の節約になるケースも珍しくありません。
さらに、優良運転者であることを証明できる「SDカード」の発行対象にもなります。このカードは、無事故・無違反の年数に応じてランクが分かれ、加盟店での買い物や宿泊費の割引などの特典を受けることができます。旅行や外食の際にも使えるため、日常生活で活用する人も少なくありません。
一方、ゴールド免許はあくまで「過去5年間の運転実績」に基づいた評価です。たとえ現在は慎重に運転していても、過去の違反履歴が残っていれば対象にはなりません。また、今後の運転で違反があれば次回の更新時にはブルーに戻る可能性もあります。
このように、ゴールド免許には経済面・時間面でのメリットが多く用意されています。安全運転を意識することが、自分自身へのご褒美にもつながる制度といえるでしょう。
マイナ免許証2枚持ち
マイナ免許証では、「2枚持ち」という運用方法が可能です。これは、従来の運転免許証とマイナンバーカード一体型の免許証(マイナ免許証)を両方保持することを指します。制度としては柔軟性がある選択肢ですが、メリットと注意点の両面を理解しておく必要があります。
まず、2枚持ちの一番のメリットは「使い分けができる」という点です。例えば、従来の免許証を運転用として携帯し、マイナ免許証を行政手続きや本人確認用として利用することが可能です。状況に応じてどちらを提示するかを選べるのは、非常に実用的です。
また、マイナ免許証の機能だけを活用したい場合でも、従来の紙の免許証に慣れている人にとっては安心材料になります。特に、マイナ免許証の読み取りに対応していない民間事業者や店舗もまだ多いため、旧来の形式を手元に残しておくことで、トラブルを避けることができます。
ただし、2枚持ちには手間もかかります。更新の際には、両方のカードを持参して手続きする必要があり、片方だけ更新する場合は未更新のカードを返納または失効手続きする必要があります。また、2枚分の発行や更新手数料が必要になるケースもあり、費用面での負担が増す可能性もあります。
さらに、どちらか一方を紛失した場合には、保有状況の変更手続きや再発行申請が必要になり、思わぬ手間が発生します。どちらのカードが有効なのか、本人が正確に把握しておく必要があります。
このように、マイナ免許証の2枚持ちは利便性とリスクのバランスが問われる選択です。自身のライフスタイルや利用場面に応じて、単独利用か併用かを慎重に検討することが大切です。特に出張や引っ越しが多い人、あるいは行政手続きを効率化したい人には、2枚持ちは有効な手段となり得ます。
マイナ免許証 いつから

DALL·E 2025 03 29 09.01.18 A horizontal image (16 9 aspect ratio) visually explaining the start date of the integrated Japanese My Number and Driver’s License card (マイナンバー一体型運転免
マイナ免許証の運用は、2025年3月24日から開始されました。この制度により、従来の運転免許証に記載されていた情報が、マイナンバーカードのICチップに電子的に統合される形となります。運転免許証とマイナンバーカードが一体化することで、行政手続きの効率化やカードの所持枚数削減を目指した新たな仕組みです。
ただし、運用が始まったからといって、すべての人が自動的にマイナ免許証に切り替わるわけではありません。現段階では「希望者のみ」が対象であり、自分で切り替えを申請しない限り、現在の運転免許証はそのまま使い続けることが可能です。また、導入初期は全国一斉ではなく、自治体ごとの対応状況や設備の整備に応じて段階的に進められるとされています。
さらに、マイナ免許証を利用するには、マイナンバーカードをすでに取得しており、署名用電子証明書が有効になっていることが前提となります。カードの暗証番号が不明だったり、有効期限が切れていたりする場合には、更新や再発行の手続きが必要です。
一方で、従来の免許証も当面は有効であり、切り替えを強制されることはありません。そのため、自分の生活スタイルや利用場面に合わせて、導入時期を検討する余地があります。たとえば、引っ越しや結婚などで住所や氏名の変更が予定されているタイミングでの切り替えが、手続きの簡略化という点では最もメリットを感じやすいでしょう。
このように、マイナ免許証は2025年春から導入されましたが、利用開始のタイミングは人それぞれです。生活にあわせた最適な時期を見極めることが、スムーズな移行につながります。
マイナ免許証 切り替え 方法
マイナ免許証への切り替えは、運転免許センターや一部の警察署で手続き可能です。事前準備と正しい手順を踏むことで、スムーズに切り替えることができます。ここでは、一般的な流れと注意点を紹介します。
まず、切り替えには「有効なマイナンバーカード」が必要です。まだカードを取得していない場合は、先に市区町村で申請を行い、カードの受け取りを済ませておく必要があります。すでに持っている人も、有効期限や暗証番号の設定状況を確認しておきましょう。特に「署名用電子証明書」が有効でないと、手続きが進められません。
次に、免許センターまたは対応する警察署へ行き、窓口で「マイナ免許証への切り替えを希望する」旨を伝えます。事前予約が必要な地域もあるため、各自治体の警察・運転免許センターの公式サイトで事前に確認しておくと安心です。
申請時に必要なものは以下の通りです:
-
マイナンバーカード(署名用電子証明書付き)
-
現行の運転免許証
-
更新通知のはがき(更新時の場合)
-
暗証番号(署名用6~16桁、利用者証明用4桁)
窓口ではこれらの情報をもとに、マイナンバーカードのICチップへ運転免許情報を記録する作業が行われます。このとき、署名用電子証明書の暗証番号の入力が必要となります。
切り替え方法には3つの選択肢があります。1つ目は「マイナ免許証のみにする」パターンで、従来の免許証は返納されます。2つ目は「従来の免許証とマイナ免許証を両方持つ」方法で、いわゆる2枚持ちになります。3つ目は「従来の免許証のままにする」選択で、切り替えを見送ることも可能です。
手続き自体は30分~1時間程度で完了し、その場で利用できるようになります。ただし、国外運転時には従来の免許証が必要な場合があるため、海外に行く機会が多い人は注意が必要です。
このように、必要なものと流れを事前に把握しておけば、マイナ免許証への切り替えは特に難しくありません。自分にとっての最適な運用方法を見極めながら、切り替えを検討してみてください。
マイナ免許証読み取りアプリ
マイナ免許証の情報を確認するには、スマートフォン向けの「マイナ免許証読み取りアプリ」が便利です。専用機器がなくても、自宅や外出先で簡単に免許情報を確認できるようになるため、導入以降、利用者が増えています。
このアプリは、iOS・Android・Windowsに対応しており、App StoreやGoogle Play、Microsoft Storeから無料でダウンロードできます。スマートフォンにNFC(近距離無線通信)機能が搭載されていれば、カードをかざすだけでICチップ内のデータを読み取ることが可能です。
使い方はシンプルです。まず、アプリを起動したら、画面の指示に従ってマイナンバーカードを読み取る準備をします。次に、署名用電子証明書の暗証番号(6~16桁)や利用者証明用暗証番号(4桁)を入力し、スマートフォンをカードの上にかざします。読み取りが完了すると、運転免許証の種類や有効期限、ゴールドかブルーかといった区分情報が画面に表示されます。
このアプリの利点は、オフラインでも利用できる点です。インターネット接続が不要なため、通信環境に関係なく情報確認が可能です。また、読み取った情報を画像として保存する機能もあり、必要に応じて第三者への提示も行えます。
一方、対応端末でない場合や、NFCの読み取り精度が低い場合にはうまく動作しないことがあります。また、入力する暗証番号を忘れているとアプリの利用自体ができないため、事前の管理も重要です。
このように、マイナ免許証読み取りアプリは、従来の免許証では得られなかったデジタル管理の利便性を提供しています。活用することで、免許情報の確認がより身近でスムーズになるでしょう。特に、ゴールド区分かどうかを簡単に確認したい人にとっては、有効なツールです。
マイナ免許証 どこで
マイナンバーカードと運転免許証の一体化により誕生した「マイナ免許証」。この手続きを行う場所や方法について、詳しくご説明いたします。
まず、マイナ免許証の取得手続きは、各都道府県の運転免許センターや一部の警察署で行うことが可能です。ただし、手続きが可能な施設や受付時間は地域によって異なるため、事前にお住まいの地域の警察署や運転免許センターの公式ウェブサイトで確認することをおすすめします。例えば、東京都の場合、運転免許試験場や運転免許更新センター、指定警察署で手続きが可能です。ただし、手続き内容によって対応可能な施設が異なるため、詳細は警視庁の公式サイトで確認が必要です。
手続きの際には、以下のものを持参する必要があります:
-
有効なマイナンバーカード:有効期限内であることを確認してください。
-
現在の運転免許証:有効期限内のもの。
-
署名用電子証明書の暗証番号:6~16桁の英数字で、市区町村でマイナンバーカード申請時に設定したものです。
手続きの流れは以下の通りです:
-
受付:指定された窓口で手続きを開始します。
-
必要書類の提出:上記の持参物を提出し、必要な申請書類を記入します。
-
手数料の支払い:更新手数料や講習手数料を支払います。手数料は所持形態や講習区分によって異なりますので、事前に確認してください。
-
適性検査:視力検査などの適性検査を受けます。
-
写真撮影:新しい免許証用の写真を撮影します。
-
講習受講:更新時講習を受講します。オンライン講習を受講済みの場合は免除されることがあります。
-
マイナンバーカードへの免許情報書き込み:マイナンバーカードに免許情報を記録し、マイナ免許証としての機能を付加します。
手続きには一定の時間がかかるため、余裕を持って訪問することが望ましいです。また、事前にオンライン予約が必要な場合もありますので、公式サイトでの確認をお忘れなく。
以上が、マイナ免許証の取得手続きを行う場所とその方法についてのご案内です。手続きをスムーズに進めるためにも、事前の情報収集と準備をしっかり行いましょう。
総括:マイナ免許証のゴールド見分け方
-
マイナ免許証ではカード表面に色区分が表示されない
-
ゴールドかブルーかの確認はICチップで行う
-
専用端末で暗証番号を入力し情報を確認できる
-
マイナポータルと連携することで自宅でも確認可能
-
スマホアプリを使えばiPhoneやAndroidで読み取り可能
-
NFC対応のスマホが必要で、古い端末は非対応の場合あり
-
マイナンバーカードの署名用電子証明書が必須
-
有効期限や免許の種類もチップ内で管理される
-
ゴールド免許は過去5年無事故・無違反で交付される
-
見た目は従来の免許証と全く異なり、色表示がない
-
従来の帯色による判別は不可能になっている
-
読み取り環境がない施設では確認が難しいこともある
-
情報を確認するには暗証番号の事前準備が必要
-
ゴールド区分は保険割引などのメリットに関わる
-
2枚持ちにすれば従来免許証での提示も可能になる
その他の記事


