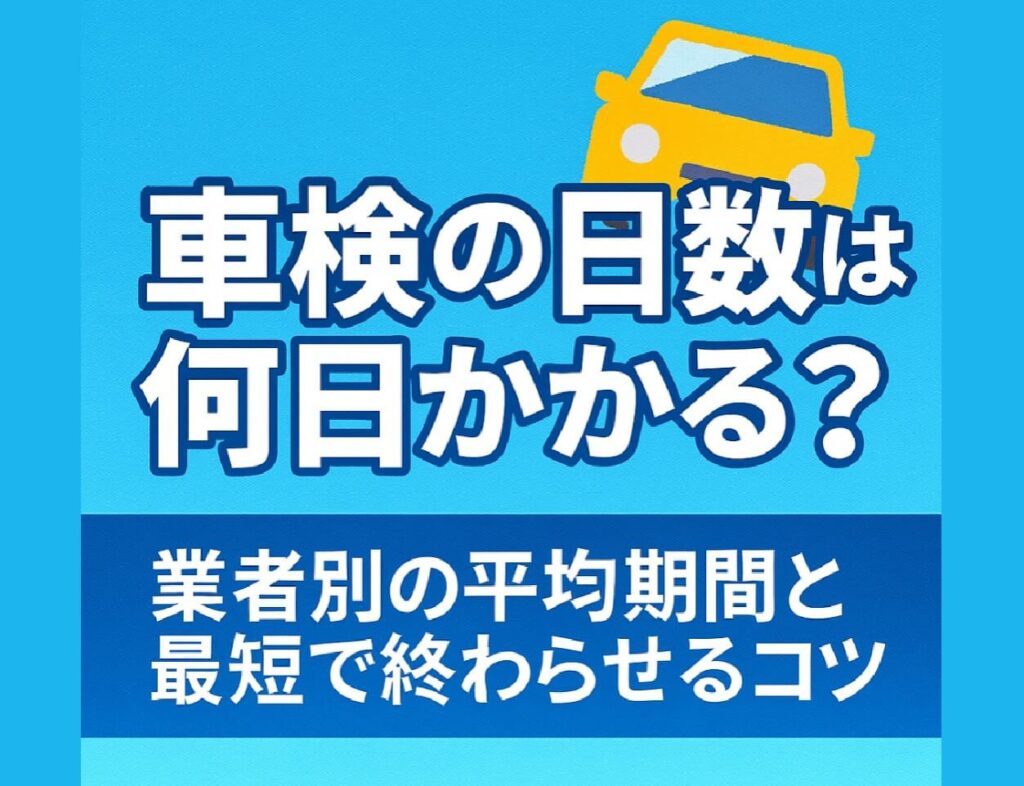こんにちは。車の広場 運営者のヨコアキです。
車検の日数が何日かかるのか分からなくて、スケジュール調整に頭を悩ませていませんか。通勤や買い物で毎日車を使っていると、車検で数日間も車が使えなくなるのは本当に困りますよね。仕事の都合で平日には時間が取れなかったり、代車が借りられるか不安だったりと、期間に関する悩みは尽きないものです。
この記事でわかること
- 車検にかかる日数の目安が依頼する業者ごとに具体的に分かります
- 即日で終わる車検と数日かかる車検の決定的な違いが理解できます
- 2025年の法改正によって変わる車検の受け方が把握できます
- 自分のライフスタイルに合った最適な車検依頼先の選び方が見つかります
・車検はどこが安い?費用相場とおすすめ業者を徹底比較車検はどこが安い?費用相場とおすすめ業者を徹底比較
車検の日数は何日かかるか業者別の平均目安
車検を依頼する場所によって、戻ってくるまでの期間は驚くほど違います。「どこにお願いしても同じ」と思っていると、予想外に時間がかかって予定が狂ってしまうこともあります。まずは、依頼先ごとの標準的な日数をチェックして、自分のスケジュールに合うか確認してみましょう。
ディーラー車検の平均期間と安心感

自動車メーカーの看板を掲げている正規ディーラーに車検をお願いする場合、一般的には2日から3日程度(1泊2日〜2泊3日)かかると考えておくと良いでしょう。私の経験でも、朝一番に車を預けて、翌日の夕方以降、あるいは翌々日に返却というパターンが最も多いですね。土曜日に預けて日曜日の夕方に受け取る、といった週末を使ったスケジュールを組む方が多いのも特徴です。
なぜ即日で終わらずに数日かかるのかというと、ディーラー車検の最大の目的が「車検に通ればOK」という最低限のラインではなく、「次の車検までの2年間、お客様に安心して乗り続けてもらうこと」にあるからです。彼らはメーカーの看板を背負っていますから、車検を通した直後に故障するような事態は絶対に避けたいと考えます。そのため、国の基準を満たしているかの検査だけでなく、メーカー独自の厳しい基準に基づいた点検を行います。
これを業界では予備整備(予防整備)と呼んだりしますが、今はまだ壊れていなくても、次の2年以内に寿命を迎えそうな部品(例えばブレーキパッドの残量が半分以下、ゴムベルトに小さなヒビ割れがある等)があれば、積極的に交換を提案してくれます。「過剰整備ではないか?」と感じる方もいるかもしれませんが、外出先でのトラブルを未然に防ぐという意味では、非常に理にかなった提案だと言えます。
品質と信頼性は間違いなくトップクラスですが、丁寧な点検と予防的な部品交換を行うため、物理的な作業時間は長くなる傾向があります。その分、整備保証が付帯するなどアフターフォローは万全です。
また、交換部品が必要になった場合の物流事情も日数に影響します。オイルやフィルターなどの消耗品は店舗に在庫がありますが、車種固有の部品や、少し珍しい部品となると、メーカーの部品センター(パーツセンター)から取り寄せる必要があります。通常は翌日に届きますが、センターにも在庫がない場合や、年式の古い車で部品製造が終了に近い場合などは、取り寄せに数日を要することがあります。結果として、当初の予定よりも伸びて1週間ほど預けることになるケースもゼロではありません。
さらに、ディーラーでは車検のタイミングに合わせて、メーカーからのリコール(無償修理)やサービスキャンペーンの作業を同時に実施してくれることがあります。これらの作業時間が追加されることも、預かり期間が長くなる一因です。ただし、代車に関しては最新モデルの試乗車を用意してくれることも多く、快適に過ごせる点は大きなメリットと言えるでしょう。
車検専門店の即日対応と早い理由

「車検のコバック」「ホリデー車検」「速太郎」などの車検専門フランチャイズ店は、その名の通り車検に特化したサービスを展開しており、スピードと価格のわかりやすさが大きな特徴です。車の状態に問題がなければ、最短45〜60分で完了するケースもあり、長くても朝預けて夕方受け取れる“即日〜1日車検”が中心となります。
こうした短時間車検が実現しているのには、明確な理由があります。
■ 徹底した予約制でムダな待ち時間を排除
専門店の多くは完全予約制を採用しており、飛び込み対応を基本的に行いません。
あらかじめ作業スケジュールが組まれているため、
-
リフト待ち
-
整備士の空き待ち
-
書類処理の順番待ち
といったムダな時間が発生しにくく、作業がスムーズに進みます。
■ チーム制による効率的な作業フロー
車検専門店では、作業工程が細かく分業化されていることが多く、
-
下回り点検担当
-
エンジンルーム担当
-
書類担当
-
検査ライン担当
といった形で複数スタッフが同時並行で作業を行います。
F1のピット作業ほどではありませんが、無駄のない動きで進められるため、作業時間が短縮される仕組みです。
初めて利用した際、ピット作業の見える化や整然とした動きに驚く方も多いでしょう。
■ 立ち会い説明で「確認待ちのロス」を防ぐ
多くの専門店では、リフトアップした状態の車をお客様と一緒に確認しながら説明する立ち会い型点検が採用されています。
-
「ここは交換が必要です」
-
「ここはまだ使用できますがどうしますか?」
とその場で判断できるため、後から電話で確認する必要がなく、作業が止まらず進む=時短につながるのです。
また、ユーザー自身が状態を目視できるため、納得感の高さも大きなメリットです。
■ ただし“短時間車検=どんな車でも可能”ではない
注意点として、これらの短時間仕上げは比較的コンディションの良い車を前提としています。
例えば、
-
ドライブシャフトブーツ破れ
-
オイル漏れ
-
部品劣化による交換
-
追加整備や調整が必要なケース
などがある場合は、部品の取り寄せや調整作業に時間がかかり、即日返却が難しい場合があります。
場合によっては、
-
一度車を預けて後日受け取りになる
-
部品入荷後に再来店が必要
といったケースもあります。
✔︎ 専門店を利用する際の心構え
「問題がなければ1時間で終わるけれど、整備内容次第では数日かかることもある」
この前提を知っておくと、予約時や来店時に慌てずに済みます。
ガソリンスタンドやカー用品店の日数
ガソリンスタンドやオートバックス、イエローハットなどのカー用品店でも車検を受け付けています。普段から利用している店舗なので相談しやすく、「気軽さ」という点では魅力的な選択肢です。ただし、車検にかかる日数は店舗の設備体制によって大きく変わるため、事前確認が欠かせません。
■ 指定工場併設タイプ:最短即日〜1日で完了するケースも
店舗の敷地内に検査ライン付きの指定工場が併設されている場合、車検専門店とほぼ同じ体制で作業が進められます。
そのため、条件が合えば、
-
午前預け → 夕方返却
-
作業内容次第では当日完了
といった形で、短期間で車検が終わることもあります。
またカー用品店の場合は、
-
タイヤ
-
バッテリー
-
ワイパーゴム
-
エアフィルター
などの消耗品が店内に豊富に在庫されているため、部品待ちによる作業停滞が起こりにくい点もメリットです。
■ 提携工場へ搬送するタイプ:受け渡し完了まで数日かかることが多い
一方、受付窓口は店舗にあるものの、整備や検査は提携工場(多くは認証工場)へ移動して実施するケースもあります。
特にガソリンスタンドはこの方式が一般的で、
-
車の移動時間
-
提携工場の混雑状況
-
部品手配時間
といった要素が追加されるため、2〜5日程度かかるケースが多い傾向にあります。
「近い=早い」というイメージを持ちやすいですが、必ずしも即日対応できるとは限らない点には注意が必要です。
■ 代車事情にも差があるので要チェック
ガソリンスタンドやカー用品店で車検を依頼する場合、代車の台数や車種は店舗によって大きく差があります。
-
代車が空き待ちで予約が遅れる
-
古めの軽自動車しか残っていない
-
プランによっては代車なし割引がある
といったケースもあるため、入庫前に確認しておくと安心です。
■ 申し込み前に聞くべき質問
迷ったときは、店舗で以下の質問をすると見積もりや納期が具体的になり、失敗しにくくなります👇
「この店舗で検査まで行いますか? それとも別の工場へ移動しますか?」
「追加整備が必要な場合、返却日は変わりますか?」
「代車は利用できますか?いつから借りられますか?」
この確認だけで、納期のイメージ違いや後悔が大幅に減ります。
■ 日数がかかっても“選ぶ価値があるケース”もある
ガソリン代割引や洗車無料など、店舗独自の特典がつくことも多く、トータルで見るとコスパが良い場合もあります。
「すぐ受け取りたい」より
「お得に済ませたい」「いつも利用している店が安心」
という方には、十分魅力的な選択肢です。
ユーザー車検の所要時間と平日限定の壁

ユーザー自身が運輸支局(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)へ車を持ち込み、検査を受ける「ユーザー車検」。最大の魅力は、代行手数料がかからず、法定費用だけで済む圧倒的なコストの安さです。
ただし、その代わりに必要になるのが、時間・手間・段取り力。業者依頼とは比較にならないほど、実務負担が大きい方式であることは理解しておく必要があります。
■ 実際にかかる時間は?
検査ラインを通す作業自体は慣れていれば10〜20分ほどで終了します。
しかし、これはあくまで「検査ライン上の時間」。
実際には次の手続きが必要です👇
-
OCR申請書や重量税納付書の購入・記入
-
証紙・印紙の購入と貼り付け
-
自賠責保険の加入・更新
-
受付窓口への提出
これらの工程を含めると、どんなに順調でも半日程度は必要になります。
■ 最大のハードル:平日限定&時間制限
運輸支局は基本的に平日の昼間(16時頃まで)しか開いていません。
土日祝日は完全に休業のため、会社員の方は有給休暇を1日確保する前提でスケジュールを組む必要があります。
💡つまり、「費用の節約」と引き換えに、「平日1日分の時間コスト」を支払う、という考え方になります。
■ よくある落とし穴:不合格(再検査)の可能性
プロによる事前点検なしで挑むため、一発合格できないケースは珍しくありません。
特に👇は落ちやすい項目です。
-
ヘッドライト光軸ズレ
-
サイドスリップ(横滑り量)
-
排ガス数値不適合
不合格の場合、その日のうちに最大3回まで再受験できますが、多くの場合、
→ 近くの「テスター屋(予備検査場)」へ移動
→ 有料で調整
→ 再び陸運局へ戻り再検査
→ 行列に並び直す
…という流れになります。
この作業で数時間消えることも珍しくありません。
もし当日中に受からなければ、限定自動車検査証を発行してもらい、後日再挑戦となります。
つまり、再び休みを取る必要が出る場合もあります。
■ 結論:ユーザー車検は「安いけれど、甘くない」
ユーザー車検は、費用面では非常に魅力的ですが、
-
平日対応必須
-
書類・準備・行動力が必要
-
再検査リスクがある
という性質上、「半日で終わるはず」と予定を入れるのは非常に危険です。
🔍 余裕を持って丸1日空けておくのが現実的です。
民間整備工場の柔軟な対応と完了期間
街中にある個人経営の整備工場や、「○○モータース」といった名称の地域密着型工場に車検を依頼する場合、作業完了までの目安は2日〜5日程度です。ディーラーや大手チェーンのように作業工程が完全にシステム化されているわけではなく、工場ごとに対応スピードや運営体制に差がある点が特徴です。
■ なぜ時間がかかることがあるのか?
多くの民間工場は少人数で運営しており、場合によっては整備士が1〜2名のみというケースもあります。
そのため、
-
他車の修理対応
-
突発的な故障対応
-
提携先作業との段取り
など、状況によっては着手が遅れることがあります。
また、部品の在庫を常備していない工場が多く、必要部品は都度発注するスタイルのため、部品の取り寄せ期間が日数に影響するケースもあります。
■ 「遅いだけ」ではなく、民間工場ならではの魅力がある
こうした運営体制だけを見ると、民間工場はスピード面では劣るように感じられるかもしれません。
しかし、それ以上に評価されているのが柔軟な対応力と相談しやすさです。
例えば、
「通勤で使うので、明日の朝までに返せませんか?」
といった無理めの相談にも、状況が許す範囲で調整してくれたり、夜まで作業して対応してくれる工場もあります。
また費用面では、
-
リサイクル部品(中古部品)
-
リビルトパーツ(再生部品)
といった予算に応じた修理方法の提案をしてくれることもあり、ディーラーより費用を抑えられるケースもあります。
■ 代車事情:期待しすぎず事前確認が安心
代車を無料で貸してくれる工場も多いですが、台数が限られていることが多く、
-
古めの軽自動車
-
タイミングによっては代車待ち
といった状況も珍しくありません。
依頼前に代車の有無や予約状況を確認するのがおすすめです。
■ こんな人に向いている
民間工場は単なる作業場ではなく、言うなれば「愛車のホームドクター」のような存在です。
-
車検だけでなく、日常の相談もできる方がいい
-
気軽に話せる整備士に任せたい
-
コストを抑えつつ必要な整備だけお願いしたい
という人にとって、民間整備工場は非常に相性の良い選択肢と言えます。
車検の日数は何日かかるかを左右する重要要因
ここまで業者ごとの平均を見てきましたが、実は「どこに頼むか」以外にも、車検にかかる日数を大きく左右する構造的な理由があります。これを知っておくと、見積もりの際により正確な日数が読めるようになりますよ。
指定工場と認証工場の違いで変わる期間

これが車検のスピードを決定づける、一番重要なポイントかもしれません。一見すると同じように見える整備工場でも、法律上は国から認められた「指定工場」と「認証工場」の2種類に明確に区分されており、どちらで受けるかで所要時間が劇的に変わります。
| 種類 | 特徴・権限 | 日数の目安 |
|---|---|---|
| 指定工場 (民間車検場) |
工場内に国の検査場と同等の検査ラインと検査員を持っている。 その場で保安基準適合証を発行できるため、車を持ち出す必要がない。 |
早い (即日〜1日) |
| 認証工場 | 分解整備を行う設備と技術はあるが、検査ラインを持っていない。 整備後、車を国の検査場(陸運局)に持ち込んで検査を受ける必要がある。 |
時間がかかる (2日〜数日) |
指定工場は、いわば「ミニ陸運局」のような機能を持っています。自社で検査を完結できるため、書類の手続きさえ後で行えば、車自体は土日や祝日であっても検査を通して合格させることができます。これが即日車検を可能にしている理由です。
一方、認証工場はどんなに整備技術が高くても、最終的な「合否判定」を下す権限を持っていません。そのため、平日の日中に陸運局まで車を運転して持ち込み、検査ラインを通す必要があります。この「移動」と「検査場での待ち時間」が必ず発生するため、物理的に即日完了させることは非常に困難なのです。
見分け方は看板です。指定工場には「指定自動車整備事業」という看板(青色であることが多い)があり、認証工場には「認証自動車整備事業」という看板(黄色であることが多い)が掲げられています。もし分からなければ、電話で「そちらは指定工場ですか?」と聞くのが一番早くて確実です。スピード重視で即日終わらせたいなら、迷わず「指定工場」を選びましょう。
代車なしプランや土日対応の可否
車検専門店のスピード重視メニューの中には、「代車なし」を条件に時間を短縮し、さらに費用も割引にするプランが存在します。これは、代車を用意したり、貸出時の傷チェックや保険説明をしたりする時間をカットすることで、作業効率を上げているためです。「店舗でコーヒーを飲んで待っている間に終わらせる」というスタイルですね。
逆に、「車を預けて仕事に行きたいから代車は必須」という場合は、代車の空き状況によって入庫日が左右されることがあります。特に繁忙期は代車が全車貸出中ということも珍しくなく、「車検はできるけど代車がないから来週にしてほしい」と言われるケースもあります。
また、先ほど触れた「指定工場」であれば、土日祝日でも自社のラインで検査を通すことができます。しかし「認証工場」の場合は、土日に車を預かることはできても、実際に検査に行けるのは月曜日の朝以降になります。つまり、土日に預けると自動的に「1泊2日」以上が確定し、さらに月曜日に返却されるかどうかも工場のスケジュール次第となります。
「平日は仕事で車を使えないから、週末だけで完結させたい」という方は、そのお店が「土日に検査まで完了して車を返してくれるか(=指定工場か)」を確認することが必須条件となります。
部品交換や3月の繁忙期に伸びるケース
車のコンディションや、車検を受ける時期(カレンダー上のタイミング)も日数に大きく影響します。特に注意が必要なのが、輸入車(外車)や、製造から20年以上経過しているような旧車に乗っている方です。
国産の大衆車であれば、部品は近くの部品商に在庫があり、半日あれば届くことがほとんどです。しかし輸入車の場合、国内在庫がなく「本国(ドイツやアメリカなど)からの取り寄せ」になるケースがあります。こうなると、船便や航空便の都合で2週間〜1ヶ月待たされることも稀ではありません。車検満了日が迫っている状態でこの事態になると、部品が届くまで「車検切れ」で乗れなくなってしまうリスクがあります。
3月は自動車業界にとって最大の繁忙期です。決算期で車の販売台数が増えるだけでなく、就職や転勤などの新生活準備で車検を受ける人が激増します。いわゆる「車検渋滞」が起きて、工場も陸運局もパンク状態になります。
普段なら即日で終わる作業でも予約が取れなかったり、「検査ラインが混みすぎて今日中に通せなかった」と数日預かりになったりすることが頻発します。
2025年の法改正で変わる受検期間
ここで、これから車検を迎える方に大切なお知らせがあります。
2025年(令和7年)4月1日から、車検の受検可能期間が正式に拡大されました。
これまでは、車検満了日の 「1ヶ月前」からしか受検できない 制度でした(※指定工場の場合のみ45日前まで対応可能という例外あり)。
しかし現在は、制度改正により、車検満了日の「2ヶ月前」から受けられるようになりました。
■ なぜ制度が変わったのか?
理由は、毎年3月に集中する「車検ラッシュ」解消のため。
特に3月末に車検期限を迎える車は非常に多く、これまでは 2月末〜3月に受検が集中していました。
制度改正により、従来より早い時期、例えば:
-
満了日:3月末
→ 1月末から受検可能に
となり、ユーザー側も整備工場側も、より余裕を持ってスケジュール調整できるようになりました。
■ 「早く受けると損する?」→ ご安心ください。
受検可能期間内であれば、いつ受けても次回の車検満了日は短縮されません。
つまり:
早めに受ける=車検の有効期間が減る
ということはありません。
📌 ポイントまとめ
-
車検は満了日の2ヶ月前から受けられる(2025年4月〜)
-
早めに受けても次回の車検期限は変わらない
-
年度末・繁忙期の混雑回避が可能
-
予約枠が取りやすく、代車待ちリスクも低減
特に、車検期限が2月〜4月に集中しているユーザーは、早期受検が非常に有利です。
繁忙期は予約が埋まりやすく、代車不足や部品待ちによる納期遅延も起こりやすいため、早めの手配が安心です。
📎 出典:国土交通省|報道発表資料「来年4月より、車検を受けられる期間が延びます」
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000645.html)
OBD検査の導入による作業時間への影響

最近の車は「走るコンピュータ」と言われるほど、自動ブレーキやレーンキープアシストなどの高度な電子制御装置が搭載されています。これに対応するために、「OBD検査」という新しい検査制度が始まっています(国産車は2024年10月から、輸入車は2025年10月から開始)。
OBD検査とは、専用の診断機(スキャンツール)を車のコネクタに接続し、車のコンピュータ内部に記録された「故障コード(DTC)」を読み取って合否を判定するものです。これまでの車検は、ブレーキが効くか、ライトが点くかといった「目に見える・測定できる」検査が主でしたが、これからは「目に見えない電子回路」の健全性もチェックされることになります。
スキャンツールを繋いでデータを読み取る作業自体は、数分で終わるため、順調にいけば全体の所要時間に大きな影響はありません。しかし問題は、万が一「不合格のコード」が見つかった場合です。センサーのズレやカメラの異常などが検知されると、特定整備認証を持つ工場で精密な診断を行い、専用のターゲット(的)を使ってカメラやレーダーを正しく調整する「エーミング作業」が必要になります。
このエーミング作業は、専用のスペースと機材、そして高度な知識が必要なため、場合によっては数時間、あるいは設備のある工場への回送が必要になり、車検日数が大幅に伸びる可能性があります。
警告灯が点灯していなくても、内部的にエラーコードが残っている場合があります。電子制御満載の新しい車にお乗りの方は、昔ながらの機械的な整備だけでなく、こうしたデジタルな検査の時間も含まれることを頭の片隅に置いておいてくださいね。
まとめ:車検の日数は何日かかるか再確認

車検にかかる日数は、単純に「作業時間」だけでなく、依頼する業者のタイプ(指定工場か認証工場か)、整備の方針(予防整備をするか最低限か)、そして時期や車の状態によって大きく変動します。最後に、ニーズ別の選び方をまとめておきましょう。
- とにかく急ぎたいなら:
「指定工場」の看板がある車検専門店、または大手カー用品店・GSを選びましょう。予約さえ取れれば即日〜1日で完了します。 - 質と安心、手厚い保証重視なら:
正規ディーラーが最適です。日数は2〜3日かかりますが、高品質な代車と安心感が得られます。 - 融通を利かせてほしい、平日動かしてほしいなら:
近所の民間整備工場に相談してみましょう。多少日数はかかっても、親身に対応してくれるはずです。
「車検 日数 何 日 かかる」と検索された皆さんの状況に合わせて、最適な依頼先を選んでみてください。そして何より重要なのは、余裕を持ったスケジュール組みです。車検切れギリギリになって焦って業者を探すと、希望の日程が空いておらず、妥協することになりかねません。2025年からは2ヶ月前から受けられるようになりますので、ぜひ早めの予約で、安全で快適なカーライフを送ってください!
その他の記事